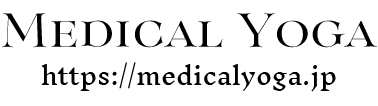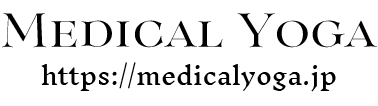扁桃体のお話:認知症とヨガ
昨日のNHK「ためしてがってん-認知症」はとても勉強になる内容でした。
http://cgi4.nhk.or.jp/gatten/archive/program.cgi?p_id=P20100915
キーワードは「扁桃体」記憶や感情を司る、脳の一部です。
認知症になると、様々なことを忘れますが「感情を伴った記憶」は忘れがたいので、「前後の脈絡は忘れても、感情だけが残る」それによって、暴言を吐いたり、拒絶をしたりするケースがあるわけです。では、感情を大切にするにはどうしたらいいでしょうか。
下記、サイトから抜粋
患者さんの感情を大切にするために、シートに患者さんの情報や気づいたことを書き込んでいくことで、患者さんの気持ちに気づき、介護の方法を見直せるように工夫されています。
(1) 介護される人の姿を「絵」に描く 絵を描くことを通じて、本人のいまの状態を客観的に見直すことができます。
(2) 介護される人の「言葉や口癖」をそのまま書く 一見無意味なように見えても、本人の言葉の裏には必ず「そのとき感じた気持ち」などの理由があります。言葉をそのまま書き出すことで、裏にある気持ちを考えるきっかけになります。
(3) (1)・(2)から気づいたことや介護のアイディアを書く 認知症になると「失われた」機能が目立ち、感情など「保たれている」機能があることになかなか気づきません。上記の(1)・(2)を通じて「保たれている」機能に気づき、それを介護に生かすことで、患者さんの症状を減らすことにつながります。
これは、認知症じゃなくても活用できると思いました。イライラしたとき、悲しいとき、日記に自分が思っていることを書き出してみると、なんでイライラするのか、なんで悲しいのか、相手はどう思っているのか、など冷静に分析できたりします。
もうひとつ、私の故郷岩手県の方が出演されていましたが、介護にこれがなくなると、認知症の症状が悪化するというのです。それは「笑顔」でした。そうはいっても笑顔になたら苦労しない、という声が聞こえてくるからこそ、せめて少しでも今日の辛さ、しんどさをさらさらと流していけるよう、介護の現場でヨガを、ヨガの深い呼吸を味わっていただける社会の動きをつくっていけたらと思っています。人は疲れ果てていたら、笑顔になんてなれるはずありませんから。それでも、笑顔こそが、何よりの薬だということが明らかになり、嬉しい番組でした!
下記、番組サイトより抜粋
認知症になると、他人の表情から気持ちを読み取る能力が低下してしまいます。しかし笑顔、つまり「相手が幸せか、幸せでないか」を読み取る能力は最後まで衰えないことがわかってきました。 介護する人が疲れたり、精神的に追い詰められたりして笑顔になれなくなってしまうと、介護される人もそれを感じて不安になってしまうことが考えられます。 専門家によると、「いま介護に疲れている人や、これから始める人は、介護保険のサービスを利用して少しでも“自分の時間”を持ち、笑顔になれる余裕を作ることが、介護される人のためにも大切だ」とのことでした。
自分の時間がもてたらぜひヨガを試してもらえたらと思います。