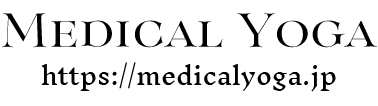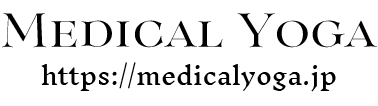あなたが生き続けるために必要な相手に私がなってあげる
ヨガはまだ「ポーズ」をとることが重視される風潮がありますが、ポーズはヨガの側面でしかありません。ポーズの本来の意味は「する」ではなく「いる」ことを大切にするという意味です。
シニアヨガに役立てようと「ユマニチュード」という概念を学んでいます。
ユマニチュードとはフランスで発案された介護の技術です。
(当時のコラムはこちら http://medical-yoga.luna-works.com/column/archives/1396 )
番組を見てすぐ、講演に申し込みをしました。
そこで学んだことをヨガを学ぶ方に伝えたいと想いこれを書いています。
講演でとても印象になった話。
人が人でいるためには、相手が必要だ。
ロビンソンクルーソーが生き続けられたのは、金曜日(ヴァンドルディ)という相方を(勝手にですが)見つけたから。でも、あなたが生き続けるために相手が必要なら、その相手に私がなってあげる、それがユマニチュードです。
ユマニチュードの背景にある哲学は「人間を特徴づけているものを大切にすれば、自然に人は生きていく」というものです。
人を人たらしめる特徴は生後から老後まで変わらない。
相手がいてコミュニケーションをする、というのも人間の特徴です。
忘れてしまっているのは介護をしている側の方なのだ。
思い出すことで幸せになるのは、実は介護される人ではなく、介護している側なのです。
ヨガの背景にあるアーユルヴェーダの根底に流れる思想も、同じですね。
生命の科学、とは「自然に反することをするとしっぺ返しを食うよ」ということです。
ユマニチュードは「技術」としての体系を確立し、技術と哲学の普及を目指しています。なぜなら、技術は、多くの人が学び、それを道具として使いこなせるようになるから。ヨガも同じようにポーズと思想というかたちで伝わってきました。
技術やポーズで魔法や奇跡を起こせるわけではないのです。
奇跡を起こせるのはただ一人だけ、それは本人の心と体です。
しかし、技術だけはやはり片手落ちなのです。技術より大切なのは、その技術が生まれた哲学です。
ヨガもユマニチュードも、それは「あなたがいてくれてうれしいわ」というメッセージです。
私たちは「あなたとの絆は要りません」という態度をとるときは、相手をみません。さわりません。話しません。褒めません。(まるで、主人と喧嘩をしたときの関係のようです)
実際、認知症の介護施設での話しかけは120秒(24時間中)、優しさを込めたまなざしは0.5秒にも満たないそうです。なぜそんなことが起こってしまうのでしょう。それは、反応しない人、面倒な人に話しかけられる人は、あたまがおかしい人か、訓練された人だけだからです。
ならば「訓練された人を増やせばいいのだ」という話なのです。
主人と喧嘩して膨れっ面をしている私に「早く話しかけてほしいな」と思って待っていてもほっておかれてしまう。それは主人が私のことをクレイジーなほどに愛してくれているか、訓練されているか、じゃないと無理だったのですね。クレイジーになってくれるか、訓練されてほしいものだと思います。
人が人として自分を認識するために必要なこと、それは
(1) 自分は話しかけられている
(2) 自分は優しく見つめられている(上から目線ではなく)
(3) 自分は広い範囲をタッチされている
そして何より人を動物と差別しうるのは(4)「自分の足で立つ」ということ。人は40秒立てれば、いろんなことができるそうです。
ヨガの基本ポーズである山のポーズはよく「きょうつけ!」と対比されます。人に言われて立たされているのか、自分の二本の脚で自尊心を持って堂々と立つのか、ということです。
これら(1)から(4) のサポートをするのが「ユマニチュード」という知識なのです。それは単に「見る、さわる、話す」というルールではなく、「どうやってみる」「どうやってさわる」「どう話しかける」つまり What より How の問題である、という点もヨガと通ずるところがあると思います。
ヨガも、どんなポーズをとるかを教えることより、どうやってとるかのアドバイスの方が大切だからです。
高齢者は私たちのルーツです。
ルーツを大切にできない社会に美しい花は咲きません。
残念なことに、人間社会に受け入れられていない、と思ってしまっている高齢者が少なくありません。それが様々な問題、孤独、無縁社会、引きこもり、などをうみだしています。
ヨガが伝えているのも「あなたは受け入れられているよ」というメッセージです。
人間社会の質を決めるのは、人同士の感情の絆。病気であってもそれを消し去ることはできない。そして、生理学的にそれは可能なのだ、というのがユマニチュードが証明を試みていることなのです。
なぜなら、記憶は劣化しても、愛情記憶、感情記憶のスピードは変わらないからです。
大脳皮質は次第に衰え、情報記憶能力、処理能力は衰えていきます。でも、好きか嫌いか、安全か危険か、などの感情記憶はいつまでたっても超高速スピードで処理されます。それは扁桃体というところでおこなわれます。
ですから、治療ではどうにもならないところをケアの力は持っている、というとき、ケアをする人は安全と認識されなくてはいけないし、好かれなくてはいけない、ということです。
まず正面から長く見つめ、視界にだんだん入っていくことが大切です。
いわばウォーミングアップから始めるヨガと同じです。
脳に「誰か来たね」と近くさせる余裕をつくるのです。
高齢者の視野が狭い、ということを知っておくことが介護のテクニックにつながります。
高齢者の関節の可動域が狭い、ということを知っておくことがヨガのテクニックにつながります。
視界に入ったら、二秒以内に笑いかけて「この人は自分を好いている」という印象を与えること。そうでなければ情報処理が始まってしまい「この人は誰だろう」という判断がされてしまう。二秒以内に、瞬時に笑顔を認識させ、扁桃体に働きかけるわけです。
また、目的を伝えるのではなく、楽しいプロセスを共有しよう、と話しかける。たとえば、体を拭きにきたんだよ、ではなく「何々さんに会いにきたんだよ♡」と。
やってあげる、ではなく、いい関係をつくる努力をする。その人に何か教えてもらえるようなことを話してもらう。
繰り返す行為があることを知っておくこともテクニックにつながる。
私たちには「自伝的遺伝子」がある。
学習したこと、記憶したこと、ノウハウ、手続きなど、反復したことの記憶は残る。長く続けたこと、手続き行動を繰り返すのは、自分を安心させるためなのだ。
だから「どこの生まれ?」「子供のころの話をする」など、その人が生きた証を一緒に確認し、受け入れ、価値を認めることはその人の今を肯定することにもつながる。
さらに、伝えるときに私たちは「伝わっているはずだ」と思い込んでしまいがちだが、伝わっているか確認することも大切。なぜなら、獣医さんは犬には概念を説明して治療をすることはないが、人のお医者さんは人に概念を説明する。テクニックだけでなく、人間観にちゃんと裏打ちしたものでコミュニケーションするのだ。
二人でケアをする。
一人が視線をとらえ語り続ける。
一人がゆっくりの動作でケアをする。
マンパワーがあることで、ケア中の想いの伝え方に余裕ができる。
これもヨガで応用できることかもしれません。
そして、長期的な視野を持つことも大切です。「嫌がったときはそのときは諦める」ヨガでいうところの「Just for Today」と同じです。
これらの試みをつづけることによって、介護される人の脳には「名前」という情報記憶は残らないかもしれないけど「いい人だ」という感情は固定されていきます。
ケアをする人は明らかに辛い状況にあります。
石を壊しているとしか思えない。
本当は宮殿を造っているかもしれないのに、です。
宮殿が見えなければ、あるいは想像できなければ仕事は雑になります。
燃え尽き症候群になってしまいます。
マニュアルで動作だけを学んでは結局石を壊していることしかわからないのです。
どうしてこれが大切なのか、ということを現場で立ち返って理解することをしなくては、マニュアルに載っていない想定外のことが起こったときに対処する力が身に付かないのです。
リハビリの本質は、誰のために、何のために、どこに行くのか、がテクニックより優先するからであり、それはケースバイケースなのです。
ユマニチュードの本はないのですか、という質問が多いそうです。
本で学ぼうとすると頭でっかちになってしまいます。看護士になりたいので、本が欲しいと言っているようなもので、本だけで学べることでは決してないのです。
私も介護ヨガの本はないのですか?という質問もよくいただきます。そのようなメソッド本はつくろうと思えば作れると思います。でも、きっとヨガをそのようなかたちで学んでしまう姿勢は
結婚式の神父さんのことば「富めるときも貧しきときも、健やかなるときも病めるときも・・・」ということばに、蛍光ペンで、そうそう、ここ大切、と「貧しきとき」と「病めるとき」をハイライトしてわかった気になってしまうのと同じことではないかと思うのです。