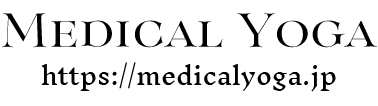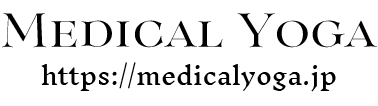病気を抱える方のクラスでの心得
Non Attachement と Practice がすべてのヨガの基本ですが、
病気を抱える方のためのクラスでは特にポーズ(アーサナ)への執着を捨てること、が求められます。
ヨガとは 気づき、呼吸、そして動き(Awareness, Breath and Movement by Nnani Chapman ) です。
私たちは往々にして、ヨガの先生ではなく、ポーズの先生になろうとしてしまいますが、
「ヨガとは」という思い込みを捨てれば、ヨガは誰にでも教えられます。
Do not Harm ( アヒンサー:非暴力)が基本です。病気を抱えた人は、もしかしたら、私たちよりもっと傷つきやすい。だから配慮が必要です。
ポーズのデモンストレーションをうまくやることよりも大事なことは、一歩引くことです。自分のヨガを人に教えるのではなく、自分のヨガを、相手にあわせ翻訳し、内面の気づきの旅にでかけられるよう、伝えること。
たくさんの言葉を並べるのではなく、必要とされることだけを語ること。
私たちは自信がないと、どうしても言葉の洪水でそれを補おうとしてしまいます。でもそれでは生徒さんに気づく余裕をつくってあげることができません。
ヨガの指導者として、ヨガとは、という思い込みにとらわれてしまうこと、これを、Occupational hazard と言います。
Practice とは、根気です。ヨガは一発で何かを治せる魔法ではありません。生徒さんと一緒に根気づよく、練習を続けていきましょう。
私はいつも、ヨガセラピーの先生は「プールサイドのライフセーバーだよ」というお話をしていますが、もっといいたとえが見つかりました。
もしかして、聞き慣れないかもしれませんが「シェルパ」(登山の際の水先案内人)です。人生という山を安全に楽しく登るためのガイド。その山道は、時に険しく、時になだらかかもしれません。時に、小さな花の存在に気づくこともあるでしょう。
外の世界に目を向ければ、日本もアメリカも、狭くて騒がしいかもしれません。でも、ひとたび、自分の内面に目を向ければ、そこには限りなく広い世界がひろがっています。自分の心の中の旅。ポーズという外形を指導するのではなく、心の中の旅に安全に誘っていく。私のナップサックは不十分かもしれないけど、あなたと安全に山に登れるよう、最大限心をはらいますね、という「安心と信頼(Safety & Trust)」を提供すること。そんなガイドになれたらいいですね。