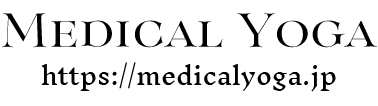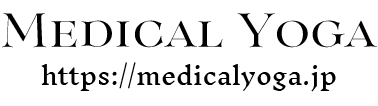ヨガの先生トライアスロンに挑戦する(第一子 Story ) – 2
《 ヨガとトライアスロンという一見正反対にみえるスポーツ 》
ストイックにポーズの練習を重ねるヨガもありますが、ヨガの本質は最終的には穏やかなこころを取り戻すことだと思っています。一方,トライアスロンは過酷さに挑戦するスポーツというイメージがあります。
ヨガとトライアスロンは一見対極にあるように見えますが、筋力、持久力、メンタル力、バランス力をすべて必要とするトライアスロンにはヨガの要素は必ず役に立つに違いないと直感的に思いました。実際、アメリカでヨガがトップアスリートのクロストレーニングとして関心を集めていることに注目していました。
もどかしいのは、日本人に向けそのことを発信できるほど、運動音痴のわたしには説得力がなかったのです。
《きっかけは恩師が勧めてくれた一冊の本》
リストラティブヨガというヨガのジャンルは私が最も積極的に普及につとめているヨガです。そのヨガを学ぶために,私はアメリカやイギリスまで勉強に出向きました。その講座の中で、私の恩師が一冊の本について触れました。私はそのとき,本の名前をノートにつづり間違えてしまったのでしょう。私は先生にメールであらためてその本の名前をたずねました。先生は「トモコ、この本はそうはみえないけど実はヨガの本なのよ。」
届いた本は,トライアスリートのお医者さんが書いた本でした。タイトルにもヨガという言葉はまったく出てきませんが、読み進めてみるとアイアンマンに挑戦するトライアスリートがいかに楽しみながら、また最小限の努力でトライアスロンの結果を出すかについて、ヨガとインドの智慧を使ってみた、という内容でした。
本を読み始めた数ヶ月後、私の主人も初めてアイアンマン70.3に挑戦することになっていましたが、彼の挑戦は彼の挑戦なので,わたしはこの本については今は言及するのを控えようと思っていました。彼は本人の準備と努力で見事初めての挑戦にも関わらず70.3マイル(スイム、バイク、ラン20km@km)を完走しました。
こんなにも過酷なレース、彼のからだでこの仮設を検証するわけにはいかない。やるなら,自己責任だ。そう思いました。
《ヨガがトライアスロンを支えてくれる》
クロストレーニングとしてのヨガをアメリカで勉強していたこともあり、ヨガがスポーツに及ぼす影響についての理論はわかっていました。
スポーツには口呼吸は致命的。鼻呼吸は換気効率をアップし、精神的な集中力も高めてくれる。
ヨガはスポーツのウォームアップ/クールダウンとして怪我を予防し、疲労の回復を早めてくれる。
ヨガはこころを穏やかにしてくれるだけでなく,集中力を高めてくれる。
ヨガは自分の弱さと向き合う勇気(ありのままの自分を見つめる勇気)をくれる。
チームスポーツの場合、ヨガは仲間の言葉に耳を傾け、思いやる寛容さを養ってくれる。
実際にトライアスロンの練習を始めてみると、その意味が実感としてよく分かりました。
ヨガ x スポーツというと、二つを組み合わせると思いがちですが、実際には違います。何も、無理矢理二つを結びつける必要はありません。二つは共通点はあれ、異なるスポーツだからです。ヨガのポーズをしながら走ったり、ヨガの姿勢で自転車をこぐ必要はありません。ヨガは,スポーツを支えてくれるのです。トライアスロンで私たちが辛さを感じるところをを補ってくれるのです。
《ヨガ的な考えで練習方法が変わる》
トライアスロンは、もちろん成果や順位を競うことに醍醐味がありますが、一方で完走した人はみな勝者という考え方があります。参加社全体がひとつのチーム,という考え方もあります。挑戦することに意義があるとすれば、楽しめるかどうかもひとつの大切なバロメーターです。
楽しめるということは、辛さを取り除くということでもあります。
ヨガの教えのひとつに「アヒムサ」という考え方があります。これは、命あるものに暴力を振るっちゃだめですよ、というものです。壮大な考えのように聞こえますが、実は基本は自分をもっと大切にね、というメッセージでもあるのです。
トライアスロンへの挑戦は、楽しんで練習し,楽しんで完走することに決めました。ヨガの教えに従えば,それができるでしょうか。
ヨガの先生トライアスロンに挑戦する(第一子 Story ) – 3 に続く