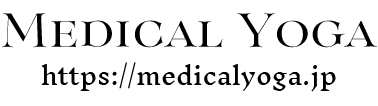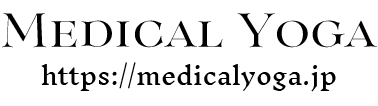ヨーガスートラの温故知新:ヨガは心の科学でありアートである
2017年夏、茨城県で初めて開催されたRYT200時間認定コースの監修をさせていただき、私自身もヨーガスートラ、マタニティヨガなどを担当しています。ヨーガスートラの教科書は伊藤武先生の
こちらを使っていますが、とてもわかりやすく、そしてインド哲学に裏付けられた説明が大変奥深いのです。
私は今回、私なりの解釈の紙芝居を作り、そしてマインドマップも活用してみました。
講座の準備をしながら、ネットを検索していたところ、私がアメリカでヨーガスートラをアメリカ人に混じって勉強していた時のメモの投稿をみつけました。最後まで読んで、投稿者を見たらびっくり!古き日の私でした(^^;;
せっかくなので、当時の解釈をご紹介させていただきます。
経験哲学 :ヨガは心の科学でありアートである
ヨガフィットでは、Yoga Sutra of Patanjali ( ヨーガスートラ オブ パタンジャリ)のテキストをつかっています。
私もまだ勉強中の身ですが、学んだことを少しずつ紹介していけたらと思います。「スートラ」とは「糸」という意味です。紡がれた物語、ということですね。
そして、ヨガ・スートラのキーワードは
「経験哲学」
ヨガにおいては、哲学(考え方)だけでは何も意味をなさず、経験(呼吸と身体に与える効能)だけでは、いわゆる Art and Science の サイエンスの部分だけになってしまうのです。
ヨガの心と身体のエクササイズの局面は「サイエンス: 科学」の領域です。でも、インド人はArt (考え方)の分野をヨガスートラとして語り継いできました。ちなみに、Art & Science とは英語で「教養」と訳されています。だからでしょうか、ヨガは西洋人にとっても「ユニバーサル」な存在として、歓迎されるのだと思います。
前書きはこれぐらいに、さて、哲学について。
Yoga Sutra は 200の教えのフレーズが、書かれています。
私が学んだ上記の本では、その一つ一つの 200のフレーズに英語の解説がついてます。
まず、もともとのyoga Sutraは、4冊の本から成り立っています。
Book 1 瞑想について Book 2 練習について Book 3 達成について Book 4 絶対について
これを、一度に覚えようともいいません。なぜなら、ヨガは経験哲学なので、私たちは連取をしながら、ながーい時間をかけて自分の経験と照らし合わせて学んでいけばいいのです。
ヨガが意図したところ:苦しみから救われたい
ヨガは、人々を苦しみから救うために生まれたものと言われています。
では、苦しみはどうして起こるのか。苦しみの原因(Klesha : クレーシャといいます)は 5つあると言われています。
1.Abidya : アビデャ : 間違った認識
2.Asimta : アスミタ : 英語では Iness などと訳されていますが、無意識な先入観
3.Raga : ラジャ : いい思い出にもとづく執着
4.Dvesha : ドベシャ : 悪い思い出に基づく嫌悪感
5.Abinivesa : アビニベサ : 恐怖心
そして、苦しみによって起きる障害(Antaraya アンタラヤといいます)には9種類あると言われています。
1.心の不調
2.身体の不調
3.迷い
4.考えずに行動してしまう
5.怠け癖
6.快楽に耽り過ぎる
7.偏屈
8.達成するまで頑張れない根気なさ
9.達成しても、飽きてすぐやめてしまう
・・・言えてる。
そして、苦しみや障害によって引き起こされる症状は4つあると言われています。
1.嫌気(抑圧された気分)
2.マイナス思考
3.身体の不調
4.呼吸の乱れ
これらの症状のうち、1-3は隠すことができるが、4の呼吸の乱れだけは隠すことができないと言われています。
Yoga Sutra の教え:素直でいなさい
Yoga Sutraにはいろんな教訓が書いていますが、つまり言っているのは「素直でいないとろくなことはないぞ」ということのように思います。
偏見を持ったり、先入観を持ったりすることが苦しみを生むのじゃよ。と言っています。
しかしながら、ヨガは経験哲学であり、生活の中に活きるものであり、山の中の仙人のように全ての執着を断ち切る必要はないのです。
ヨガをやることで心がクリアになる、と言われるのは、今、何の執着を手放せば、苦しみから逃れられるか、ということがわかるようになるからだと言われています。なので、そのときそのときの苦しみに対処していく、長いプロセスなのです。人生は旅ですから、いろんな苦しみと出会うでしょう。
Yoga Fit で繰り返し教えられる「 ヨガフィットのエッセンス」という言葉があります。
これは、ヨーガスートラの教えを現代人向けにわかりやすく言い直したものと言えるでしょう(気づいたときには私も感動しました)
1.呼吸しましょう。
2.心と身体で素直に感じましょう。
3.身体の声を聴きましょう(無理を強いてませんか?)
4.競争、比較はしないでおきましょう
5.先入観、偏見を持たないようにしましょう
6.判断を下す必要はありません
7.今、自分がこの瞬間に存在することを思い出しましょう
行き詰まったとき、苦しくなったときの解決策として、確かに言えている・・と思うことばかりです。裏を返せば、上記のことができなくなったときに、人は苦しむのではないかなー。
うちの両親もよく言っていました。素直にね。素直にね。ひねくれ者の私には、素直になるのはある意味修行。でも、素直になったときの楽な気持ち、ってあったなー。たとえば「お母さんごめんなさい」と言えたときとか。
ヨガの人生観
ヨガでは、人生を3つのステージにわけています。
1.先生や友人、親、社会など、自分の周りから学ぶ時期
2.家族を創り、社会のために生きる
3.使命を果たしたら、自分のために生きる
ですから、2では愛する人と出会い、子供を作ります。家族は一番小さな社会の単位なので、大切にします。ヨガでは禁欲、と言われますが、これは適切な欲はいいのです。家族や愛する人を悲しませないような欲の使い方をしている限りは問題ないのです。敢えて、禁欲という意志がもてはやされるのは、そういう強い意志は社会を変えたり、いい方向に持っていくときにとても役に立つからです。確固たる意志を持つトレーニングでもあるのです。
3では、孫ができるぐらいになり、自分の家庭を治める時期も卒業することになったら、今度は静かに自分のためにヨガを楽しみます。
ああ、ヨガって奥が深いなー。でも意外と言っていることは、なるほどということばかりだなーと、ヨガスートラを学びながら思います。
Yama と Faith (信義、信用、信頼)
ヨガにおけるヤマとは、本来は「手綱」の意であり、ヨガでは「禁戒(慎むべきこと)」を意味します。経典「ヨーガ・スートラ」に書かれている「アシュタンガ(八本の枝・手足)」の一項目であり、
1.アヒンサー(非暴力、傷つけない)
2.サティヤ(嘘をつかない)
3.アスティヤ(盗まない)
4.ブラフマチャリヤ(禁欲)
5.アパリグラハ(不貧、必要以外のものは持たない)
の5つからなります。
どうしてこれらのことは大事だと言われるのでしょう。逆に、これらを心がけないとどういう状況になるでしょう。
「信用」を失ってしまうのです。特に一番上にきている「非暴力」。傷つける人を信用する人はいません。信用は 英語ではFaithと訳されています。
社会で生きていくには、いろんな人との信用、信頼が欠かせません。もちろん他人だけではなく、仕事に、物に、そして自分に対する信頼も大切です。信じる力で人生は左右されると言っても過言ではないでしょう。信頼のないところでは、人は迷い、疑いによって苦しむことになります。
ただ、信用は一朝一夕に築けるものではありません。毎日の積み重ねで人は信頼を育んでいくものです。とっさに妄信的に判断する、ブラインド フェイス ( Blind Faith ) ではいけないのです。
病院でも、先生と患者さんの間に信頼関係があるかないかで回復の速度は全く違うとのことです。素直な心で接すること。ヨガの教えはこの一言につきるのではないかなー、というのがこれまで学んだところまでの感想です。
ちなみに、当時使っていた教科書(英語)はこちらです。