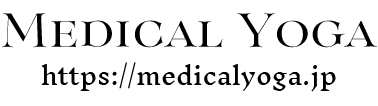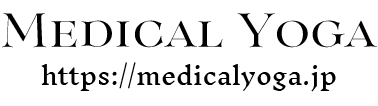産後ケアとマタニティヨガへの想い
産後ケアを知らずに母親になる
私は乳がん患者さん向けのヨガの普及にも取り組んでいるのですが、いつも「必要としている人にどうか届きますように」と願っています。それほど、現実には「存在していても届かない」という難しさがあります。
産後は知っていてもアクセスできない
産後ケアがあっても、アクセスできない現実があります。育児が始まると、お母さんの世界は途端に狭まります。一人目出産はもちろんですが、二人目、三人目でも生後の生活は小さな命を守ることに必死、あっという間に余裕がなくなることには変わりありません。
産後の情報インプットには限界があると感じています。テストのようですが出産前にある程度「傾向と対策」で産後の生活を想定しておくことが必要なのではないか、と思います。
私自身も、どうして母になる練習をしてから母にならなかったのだろう、と思った時期がありました。お母さんも一緒に成長していく、と周りは励ましてくれますが、知っておくこと、想定しておくことで防げた辛さはあったように思います。
両親学級を変えたい
妊娠がわかってから出産までの10ヶ月はあっという間です。定期的な両親学級で教えてもらうことは、夫婦ともに産後のハード面(おしめ替え、沐浴)などがメインです。
両親学級で、陣痛の時のテニスボールのあてかたなどを教えてもらうよりも、産後のお母さんの生活や、体力、メンタルがどのように変化し、多くのお母さんがどんなSOSを出しているのか、ということを夫婦で考え、それぞれの家庭なりの対策を立てらる機会が欲しいです。先輩のお母さんのお話は、もしかしたら専門家の話よりもずっと参考になるかもしれません。
マタニティヨガクラスで妊娠中からの産後ケア
お母さんにも休日を。それが産後ケアの狙いだと思っています。残念ながら日本には、お母さんが自分に時間やお金をかけることは贅沢だ、という風潮が未だ残っています。しかし、科学的にも経済的にもそれは不合理だということを広めていかなくてはならないと思います。お母さんの疲れに子供は敏感です。
お母さんを感じている子供時代
子供の脳波について知ると、子供に接する時に必要なのは理屈ではなく、雰囲気であるということがわかります。
脳波には大きくわけて、以下の4つがあります。
- デルタ(δ)波: 熟睡しているとき
- シータ(θ)波: 寝る直前のまどろんでいるとき
- アルファ(α)波:目を閉じてリラックスしているとき
- ベータ(β)波: 覚醒しているとき
子どもは新生児期から学童期へと至る過程で成長時期に応じて優勢な周波数帯域が変化します。生まれたばかりの赤ちゃんは寝てばかりいますが、脳波も眠っているときに出るデルタ波が主体です。
赤ちゃんには理屈が通用するべくもなく、お母さんが笑ったり、歌ったり、抱きしめてくれるという肌感覚が世界の全てなのです。
発達心理学で知る子供の側からの需要
そんな時に、目の前のお母さんが疲れ果て、余裕がなく、寛容さを欠いていたらどうでしょう。母親が一人の人間として幸福感を持ち、安定した心理であることなしに、子供との安定した関係や、寛容的な態度は不可能です。
マタニティヨガで事前訓練をしてほしい
ヨガのクラスだけでなく、ほとんどのご夫婦が出産前に参加される両親学級でしっかりと伝えてほしいことは、産後の現実と、家族や社会によるサポート、具体的なケアの必要性です。産後は、体も、心も一杯一杯でSOSで当たり前。ホルモンの不安定さがそれを援護射撃します。本来、新しい命を育もうとしている姿は美しく、神々しくさえあるのに、サポートも余裕もなければ時間とともに疲弊していく一方です。
今、産後のお母さんにどんなケアがあるか、と聞かれ答えられる人は限られていると思います。でも、実はたくさんのケアラーさんが手を差し伸べたいと、活動しています。
順番を間違えがちな産後
仕事、家族、自分のどれに時間を使っていますか?
仕事が大切でないわけではない、だけど私たちは往々にしていつも自分が最後。でも、そうすると結局全てがうまく回らないことが多いのではないでしょうか。仕事をするのも自分、家族と接する主体も自分です。
しかし、現実は本当に難しい。余裕のないお母さんがSOSを出せないのが今の日本の現状です。
母子手帳とともに母手帳を
日本は産後のケアを受けられるという認識が諸外国に比べ浸透していないということ。私たちの世代から、妊娠は病気ではない、という風潮に負けないようにしよう、ということ。病気ではないかもしれないけれど、命がけで産んで、命がけで育てていき、産後は超長距離走と心得るべきであること。お母さんは自分のためにもっと時間を使って良い!なぜならその方が、子供に良い影響を与えるから。ケアすることこそ、急がば回れ、につながるということ。
その手帳とともに、地域で利用できる産後ケアのイエローページのようなものを、各自治体で作成いただけたらと思います。まだまだ産後ケアというサービス自体が知られていませんが、独自に取り組みを始めている自治体もあります。
そして、一人でも多くのお母さんが、赤ちゃんを守るために自分を大切にする必要性を知ってほしい、その周りのサポート体制が社会に根付いてほしい、と願っています。
マタニティヨガを学び、伝えてほしい、産後ケアを知ってほしい
産前産後のサポートをしたいという様々な職種の方々がつながり始めています。
グループでは現在も参加者を募集されています。グループURLをクリックいただき、簡単なアンケートにお答えいただきますと入会手続き完了です。
私も知り合いの女医さんからご紹介をいただき参加しています。
産前産後ケアに関わっている方はもちろんのこと、産後のお母さんやご家族の力になりたい方、ぜひ一緒に、産後のお母さんのサポートに本当に必要なことを考えていきませんか?
私自身は、出産前のマタニティヨガを通じ、予防的な取り組みとしての啓発活動、具体的なリラクセーション法を学べる機会を創出していきたいと考えています。