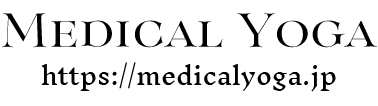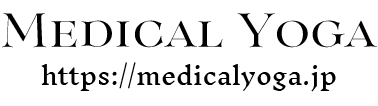胸郭出口症候群のためのリストラティブ・ヨガのポーズ
20-30代のなで型の女性に多い胸郭出口症候群ですが、主に鎖骨と第一肋骨の隙間である「胸郭出口」が何らかの原因で狭くなり、そこに通っている神経が圧迫や牽引を受けて肩周辺~手腕にかけて、痛み・しびれ・だるさを引き起こす症候群です。
これらは頸肋症候群(けいろくしょうこうぐん)、斜角筋症候群(しゃかくきんしょうこうぐん)、肋鎖症候群(ろくさしょうこうぐん)、過外転症候群(かがいてんしょうこうぐん)によってひきおこされると考えられています。原因は胸郭出口の狭さだけではなく、首の斜角筋の形状に骨格や特定の姿勢が加わって引き起こされることもあります。
狭くなった胸郭出口周辺に通っている神経が圧迫や牽引を受けると、その周辺は常に緊張状態になります。緊張状態がが続くと自律神経の交感神経が優位になり、緊張がさらに強まることで、筋肉の張りや凝り、血流障害を引き起こし、ついには痛みを引き起こしていきます。
この痛みのスパイラルを引き起こしている大きな要因は大きくわけて「神経の圧迫・牽引」と、「組織や筋肉の緊張、コリ、血流障害」の二つがあります。
治療の最悪のケースは手術になりますが、後遺症リスクや再発もある為、ほとんど行われていません。胸郭出口症候群患者9割の治療は、体操療法・運動療法等です。
しかし、いったん狭くなった出口を広げることが、魔法のように一発でできるわけはありません。前提となるのは、毎日の地道な心がけによる姿勢改善や、ストレッチになります。
悪循環のもうひとつの原因である「組織や筋肉の緊張、コリ、血流障害」に対しては、ストレッチで伸ばしたり縮めたりすることで緊張を解き、血流の改善を促し、痛みの物質を排泄するのが効果的です。神経の中にも血管が通っており、胸郭出口で圧迫・牽引された神経の中を通っている血流も悪くなっています。ストレッチにより栄養や酸素がしっかり神経へと運ばれることがなければ、痛みを生み出す物質や老廃物も上手に排泄されません。
ヨガは胸郭出口症候群の治療法として研究されているわけではありません。
しかし、筋肉の緊張を緩め、ストレッチや姿勢矯正の要素を含むヨガを日常的に取り入れることによって、上記の問題が改善され、症状を緩和できる可能性もあります。
一般的なヨガによるストレッチも悪くはありませんが、ヨガそのもののハードルが高い、という方がほとんどではないでしょうか。リハビリも、辛い辛いと思いながらやるよりは、気持ちいいと思ってやっていただいたほうが効果も早いのではと思います。また、リハビリそのものが、緊張感を与えるものであるよりは、私たちにリラックスを与えてくれるものであってほしいと思います。
リストラティブ・ヨガのポーズの中には、肋骨を鎖骨から遠ざけ、緊張した斜角筋を緩めて伸ばすのに効果的なポーズがあります。病院などで勧められるストレッチは、椅子に座って行うものが主流ですが、リストラティブヨガでは、身体を横たえ、自分の頭の重みでストレッチできるのが特徴です。
また、呼吸に意識を向けることで、腹筋を含む体幹をしっかりグラウンディングする意識をもつことで、鎖骨と肋骨のあいだにスペースをつくりやすくなります。
これは、ヨガの「魚のポーズ」のリストラティブ・バージョンを、さらに斜角筋のストレッチのために応用したものです。
用意するもの。
◎バスタオル(頭が床にあたったときに痛くないように)
◎丸めた毛布かタオルケット(ボルスターや、丸めたヨガマット、ブロックでもかまいません。)
◎枕か、丸めた毛布、タオルケット(ひざの下に置いて、お腹を緩めます)
頭の下にバスタオルをひきます。
丸めた毛布を横向きに、肩甲骨の下になるようにおきます。
ひざの下に、枕を入れておきます。
後頭部をバスタオルをしいた床につけるようにして、首の前面を伸ばします。
次に、ゆっくり、右手で左の肋骨を軽くおさえながら、頭は右側に倒します。頭の重みで、首筋が気持ちよくストレッチされるのを感じましょう。そのまま、お腹を意識して深呼吸します。お腹に意識を向け、息を吐ききるごとに肋骨と鎖骨の間の空間が広くなるのをイメージします。反対側も同様に行います。
起き上がってくるときは、必ず頭を正面に戻し、片方の手を頭のうしろに回し、片方の手で床を押しながらゆっくり起き上がってきます。決して、首が曲がった状態でそのまま起き上がったり、勢いをつけて急激に起き上がってきては行けません。
繰り返しになりますが、ポーズのポイントは、
☆頭の重みで、首を縦と横に気持ちよく伸ばすこと。
☆お腹に意識を向けて、深く呼吸を吐き出すこと。
☆首だけでなく、体全体のリラックスから、緊張をほぐしていくこと(そのためにも、ひざを緩めること)
お魚になったつもりで、気持ちよく体を委ねてみてください。