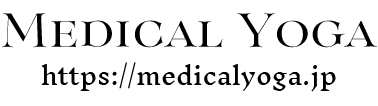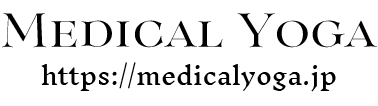ヨガと高血圧に関する研究
ペンシルバニア大学の研究です。
アメリカでは7千万人の高血圧患者がいます。高血圧は、薬はあるがなかなかコントロールできないため、薬に変わる方法はないのかという関心は高いです。
研究でも、血圧そのものだけでなく、体重管理、塩分やアルコール摂取、運動習慣などへの影響にも注目しています。
AHA (アメリカ心臓協会)でも、代替医療や予防ヘルスケアの更なる充実を求める提言がなされています。ペンシルバニア大学の研究者たちが(Debbie L.Cohen MD) 世界中のヨガと高血圧の研究を洗い出してみたところ、タイ、インド、カナダ、イギリスなどで研究はあったものの、標本数の少なさや、結果にもインパクトがあるものが見られませんでした。
薬での治療の限界が高いからこそ、ヨガが果たせる可能性があるのではないかと、研究に取り組み始めました。研究はこれまで、二つのフェイズで行われてきています。
1回目の研究は、克服すべき課題だらけでした。6週間、12週間にわたり、反応を追いかけましたが、実際には途中でヨガをやめてしまう患者さんが多かったのです。それは、ヨガのスタイルが患者さんたちが期待していたものと異なっていたこと、ヨガのやり方自体が難しかったこと、などが理由にありました。また、研究の期間ももっと長期的に行う必要がありそうでした。なので、彼女たちは研究そのものの練り直しをはかったのです。
地道な努力がなされてきていることに驚きます。
2回目の研究では、標本数を増やすために大々的に広告をうちました。まだ、中間報告の段階で、ある程度の結果は2014年を予定しているとのことです。
ハタヨガのプロジェクトに参加するグループ、栄養アドバイスと歩行(6千歩から徐々に一万歩に増やしていく)プロジェクト、両者の混合で始められました。
中間報告では、特に下の血圧の下がりが早いようだ、ということがみられます。
瞑想をすることにより、脳の島皮質や尾状核が活性化することがわかってきています。
ヨガによって、高血圧の他の危険因子を減らせるか、というテーマですが、中脳辺縁系報酬システムや、ドーパミンの分泌などとの関係は残念ながらみられなかったそうです。
研究からドロップダウンしてしまう要因の分析や、ネガティブな結果の共有など、研究の結果がどうでるかよりも、ヨガが高血圧を始め、薬や西洋医学の限界にさらされている疾病に対し、影響を与えうる可能性について、科学的に厳密な追求努力がなされている分野であるということに評価の声が集まっていたのが印象的でした。