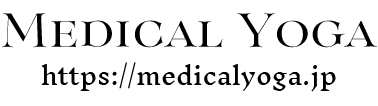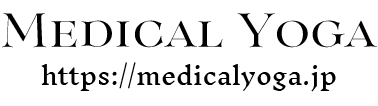大規模被災地に呼吸法を伝えてきたプロジェクト
http://www.haveahealthymind.com を主宰するRichard P. Brown 博士と Patricia L. Gerbarg 博士が行ってきた、大規模被災地でのPTSDやその他心身の問題へのアプローチを紹介します。
被災地での研究は、簡単なものではありません。突然の災害には研究資金が降りるのを待つ時間がありません。現場の倒壊、自治体の許可が得られない、層を特定してプログラムを用意することが難しい、など、通常の研究条件をそのまま適用することはほぼ不可能です。
被災地での懸命な生活状況下でどんなヨガの練習ができるのか。どんなサポートが必要なのか。
災害など衝撃の大きいストレスによる心身の不調の鍵を握るのは、なんといっても自律神経の乱れです。また、HRV (心拍変動)は、産まれたばかりの赤ちゃんや健康な人は高く、ストレスが多い人は低いのが特徴です。これは、一分間に何回呼吸をして生きているか、にも反映されます。たとえば、一分間に5回呼吸をしている人と30回呼吸をしている人とでは大きく異なります。
両氏の研究は2004年の東南アジアでの大津波にまでさかのぼります。研究を始めるにあたり、Collaboration (協力)が意味するものは Compromise (歩み寄り)だったといいます。困難な研究条件のもと、多くのボランティアの協力がありました。
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1600-0447.2009.01466.x/abstract
背景にあったのは、ヨガの呼吸プログラムがベトナム戦争の退役軍人たちのPTSDを救ったという研究です。軍人たちがベジタリアンであることは難しそうです。彼らはアルコールも大量にのみ、肉食です。ヨガのライフスタイルをそのままもちこむことは現実的ではありませんでした。
また、多くの制約の中での研究では、コミュニティのリーダーをトレーニングしていく必要がありました。そこで着目されたのが、呼吸法の安全性、簡単さです。PTSDやストレスにさらされた人たちの呼吸は速いことが多く、そのことはパニック障害や不安、高血圧、ぜんそく、鬱などの直接、間接的な要因となります。
911のあとも、全米各地で Breath Body Mind ワークショップが行われました。ヨガの呼吸法や、ゆっくりした呼吸にあわせた動き、心身の内面のスペースづくりなどです。
Less than perfect can be good enough.
完全ではないにしても、十分なことがあります。
スーダンの被害市民たちの呼吸も、襲撃への恐怖から速くて浅いものでした。この地に呼吸法を教えにいくプロジェクトもまったく容易ではありませんでしたが、実行しやすく、トレーなーも育成しやすく、コストも抑えられ、持続可能という点に着目し、研究が行われています。呼吸にあわせてからだを動かす動きも取り入れていますが、シャバアサナは難しく、クラスの終わりにはみんなで立ち上がって踊りを踊り始めてしまうのだと言っていました。