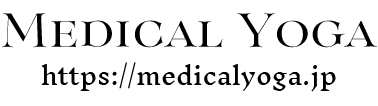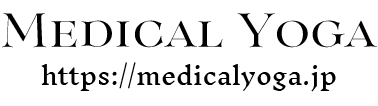ヨガセラピーをどう定義するか:ヨガが人を癒せるのはどうしてか
米国では、ヨガリサーチャーとヨガセラピストたちによって
- ヨガセラピーというものをを従来型の西洋医学/ヘルスケアとどう区別するのか
- ヨガセラピーというものをヨガとどう区別するのか
- さらに、ヨガリサーチはヨガセラピストたちをどういうかたちでサポートできるのか。
- ヨガリサーチが定めたプロトコル(研究の手順や基準)と、ヨガセラピーの現場が乖離しているギャップはどう埋めるのか。
という議論が続けられています。
従来型のヘルスケアが、特定の症状の改善にフォーカスしているのに対し、ヨガセラピーは全体システム、つまりホリスティックなアプローチなのだ、などという意見が飛び交っています。
でも、私はこう思います。
研究はヨガセラピーの発展に非常に貢献しているが、研究がすべてではないこと。ヨガはEBM(Evidenced Based Medicine ) ではなく、あくまでもPBM (Practice Based Medicine ) だということ。研究者たちと、セラピストたちの立場が異なり、そしてきっと他のプレイヤーたち、サイコセラピストたち、などとの間にも溝はあるかもしれないけれども、Collaboration は Compromise でもある。お互いが歩み寄って、いいものを作り上げていくことに意義があり、異なるものが調和していることこそが、ヨガのプロセスそのものであり、協業する価値なのでしょう。
そして、誰をもってヨガセラピストというのか。ヨガセラピストはどう定義するのか、ということに関してもこう考えています。ヨガセラピストと名乗らない多くの先生たちが、生徒さんたちにヨガの楽しさを伝え、病気の有る無しに関わらず、その人の人生をより健康な方向に促しているとしたら、その先生が行っていることは本質的にセラピーなのではないかと思うのです。
セラピーという言葉やテクニックに振り回されるのではなく、目の前の人に丁寧に自分の愛情を注げる先生こそがヨガセラピストなのではないかと思うのです。癒しは常に「双方向」だと思います。癒したつもりの相手が元気になるのを見て、癒されるのはむしろ癒した側ではないでしょうか。
ヨガセラピーの研究で、腰痛とヨガの関係性についての論文で素晴らしいものが出たとしても、ヨガセラピストたちの生徒たちは、腰痛の人に続き、首の痛み、膝の痛み、と様々なのです。ヨガセラピストたちは、ひとつの研究を、他の症例にも応用していかなくてはなりません。テクニックや研究を追いかけるのがヨガセラピストではないのです。
ヨガとヨガセラピーを明確に区別する意味があるのかな、とも思います。ヨガがもし薬になるのなら、それはCompassion Based Medicineであり得るからだと思うのです。つまり、慈悲に基づいた薬です。ヨガによる、マインドフルネスの姿勢がもたらすものは、平和であり、アヒムサ(非暴力:相手を傷つけないこと)であり、生きる苦しみや矛盾を知ることでしょう。独りよがりではなく相手の辛さを慮ることでしょう。丁寧にヨガに向き合い、それを生徒さんと共有できる先生は、みなヨガセラピスト(セラピスト、という言い方が適切かはわかりませんが)なのだと、私自身は考えます。
ヨガリサーチが存在するのは、ヨガとヨガセラピーが異なるからだと、米国のアカデミックは言います。アメリカのヨガセラピーの動きを理解するためには、米国の研究スタイルを理解することから始めなければなりません。
しかしなお、茶の湯というマインドフルネスがDNAに根付いている、禅の国でヨガを教えながら思うのです。
私たち日本人は世界のヨガリサーチを参考にさせてもらいながらも、ヨガが人の心や平和を大切にすることによる薬だという本質をきっと本能的に理解し、活用していけるのではないかと。
そんなことを言っているからグローバルスタンダードから遅れをとるのだといわれそうですが、ヨガを仕事にする以前から、遅れを取りながらもいいものを作り上げてきた日本の諸業界をみてきました。
発展し続けるヨガセラピー&リサーチを謙虚に学び、持ち帰ったものでホームグラウンドを肥やしていく、そんな仕事をしていけたらと思います。