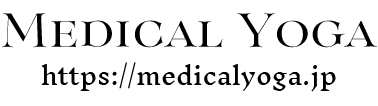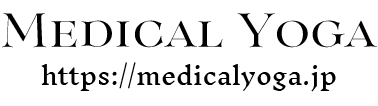ヨガと便秘や過敏性腸症候群(消化のトラブル)
私たちは普段のヨガのクラスに慣れていると、シンプルでゆっくりした動きに戸惑いを覚えるかもしれません。
しかし、セラピーとしてのヨガでは私たちの身体のエネルギーが消耗したり過剰になっているアンバランスを穏やかになだめていくのを、身体を実験室にしてやってみるのです。
消化のトラブルによく用いられるヨガのポーズは前屈、ツイスト、そしてサイドベンドです。
身体の中にこんな小さな変化を起こしてみましょう。
あおむけになり、膝を立てます。
息を吸って、胃を少し天井に向かって持ち上げます。
息を吐いて、優しく降ろします。
何回か繰り返してみましょう。
今度は、右の膝を曲げて胸に引き寄せ、同じことを行ってみます。おなかが太ももに当たり、マッサージされる感覚を味わってみましょう。
IBS(過敏性超症候群)は仙骨に問題があることが少なくありません。
こういう小さな動きを試してみましょう。
あおむけから、右の足を少し外側に開きます。呼吸をしながら、骨盤の位置を動かさず、左の足を右足にそろえてみると、左のわきが伸びると思います。今度は息を吸って、左の手を天井を通り頭上に向かって伸ばしていきます。(腕は床に置かれます)開いた左のわきに呼吸を送り込むように、もう一度ゆっくり呼吸をしてみます。息を吸って胃を少し床から持ち上げ、吐いてリラックスします。反対側も同様に行います。
呼吸でおなかをマッサージするつもりで、Cat & Cow のポーズも次のように行ってみましょう。
四つん這いから息を吐いておなかを凹ませながら、お尻を後ろにひいていき、残っている息をすべて吐ききるようにして子供のポーズになります。息を吸ってリラックスしながら、四つん這いに戻ります。
片鼻呼吸法も次のようにかなりゆっくりやってみましょう。身体に刺激を与えるのではなく、身体をなだめていくイメージです。片方の鼻から息を吸いながら、あごをあげて、すいきったらいったん息をとめます。いったん手を鼻から離し、指をかえて、息を吐きながらあごを下げながら、吐ききったら息をとめて、いったん手を鼻から離し、指を変えて、それから片方の穴で吸いながら、あごをあげていきます。自律神経がうまく働いていないからこそ、ポーズを作るのではなく、ひとつひとつの身体の動きに意識を向けたプロセスを大切にします。
前屈も、柔軟性を競うものではありません。
息を吐きながら、股関節から上半身を倒していきますが、そのときに膝は軽く曲げ、手はお尻から腿やふくらはぎの後ろをたどりながら、足首に向かいます。息を吸って、胸を開きながら身体を起こしていきます。
直立姿勢になったら、息を吐きながらおなかを凹ませていきます。これ以上凹まないというところまで吐いたら、息を吐きながら再び股関節から上半身を倒していきます。膝は軽く曲げ、手はお尻から腿やふくらはぎの後ろをたどりながら足首に向かい、このサイクルを繰り返していきます。深い呼吸による胃の動きで、内臓がマッサージされる感覚を味わいましょう。これこそが、便秘や過敏性腸症候群のからだとの対話です。
ツイストをしてみましょう。
足を開いた前屈から、左腕は床に、右腕は後ろにひいて、天井に伸ばします。
息を吸って、後ろの腕をよりひねってみましょう。首に負担をかけないために、首は無理をせず床を見るようにします。ひねりながら、ヨガのチャンティングをしてもいいでしょう。抵抗がなければ、オーム、という言葉をいいながらひねるのもひとつの方法です。
最後に2段階の腹式呼吸でおなかをマッサージしていきましょう。
息を吐きながら、おなかを凹ませていき(3カウント)息を止めて(3カウント)最後の一息を吐いていきます(3カウント)息を吸いながら、おなかを緩めていきます。波が寄せては返すように、緊張と弛緩の対象を味わってみましょう。
自分の呼吸だけで、おなかはこんなにもマッサージできるのです。
マッサージの効果だけでなく、呼吸に意識を向け、ゆっくり行うことで、自律神経の調整にもいい影響を与えるといわれています。自己観察を行う時間にもなるでしょう。