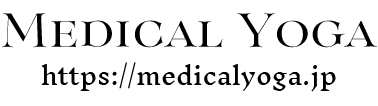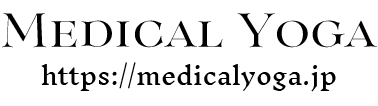乳がんヨガと医療の未来
第一回臨床試験学会にて希少性疾患の臨床研究に関するセッションでの国立研究開発法人国立精神·神経医療研究センターの小牧宏文先生のお話の中にあったキーワードをご紹介させてください。
ちなみに、難病という名称は日本独特の表現とのことで、英語ではRare Disease Orphan Diseaseと呼ばれているとのことです。(Orphan とは孤児の、とか孤立無援の、という意味)
それゆえに、人数が少ないため難病なのではなく、原因や治療法が不明の希少性疾患に苦しんでいる方の総数は実際はとても多いのです。
小牧先生は希少性疾患ケアの今後のあり方について下記の3つをお話されていましたが、病気の種類を問わずこれからの医療が目指して行く方向性について普遍的に言えることではないかと思いました。
• プロアクティブケア
• シェアリング
• エンパワーメント
(1) プロアクティブケア、というのは、悪化を予防する手立て。先回り、先制医療とも言われる。自然歴を踏まえて、定期検査、ケアを積み重ねていく姿勢。
自然歴、というのは、その病気を何もせずに放っておいたらどうなるか、ということです。乳がんも、治療だけ、と治療に+αでケアがあるかどうか、でずいぶん変わってくるという見方はできるかと思います。
(2) 患者さんや家族と、(臨床研究の)労力をシェア、データをシェア、成果をシェア
(3) エンパワーメントを訳すとしたら、啓蒙は上から目線すぎるため不適切であると考える。啓発、という意味合いに近い。人々に夢や希望を与え、勇気付け、本来持っている素晴らしい生きる力を湧き出させること。
とのことでした。これらのことは乳がんヨガが担えることにも通ずるのではないかと思います。
できるだけ早い段階でヨガに出会っていただければ患者さんが抱えるであろう、不安や生活上の不便に、できるだけ先回りして手を打って行くことができるかもしれません。
ヨガを通じて友人ができたり、自分自身の生活が変わったりしたことを、決して押し付け合うことなく、シェアしていけたら。
そして病気と闘うのではなく、自分の心と向き合いながら人生を豊かにしていくために、ヨガが役割を果たすことができたら、そのようなことをまだヨガと出会っていない患者様に知っていただけたら、と思いました。
乳がん患者さんのためのヨガを学んだ方々が、自分たちは何を学び、社会にどういうことを還元していけるのか、ということを再確認するキーワードになればと思い、お伝えさせていただきました。
乳がんヨガのBCY Institute Japan のウェブサイトはこちらになります。
https://breastcancer-yoga.org