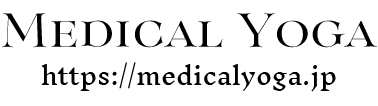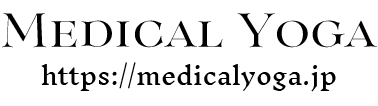ブータンにヨガのエッセンスを探しに
タラップに降り立つクラシックな旅行
空港に降り立って驚いたのは、その小ささ。建物は伝統様式で装飾されており、滑走路は一本だけ。格納庫も所有する飛行機も4台のみ。乗り入れ航空会社は一社のみ(だから迷うこともない)それで間に合うように国の大きさを制限し、維持していることがまずすごいと思いました。歴史的に、どんな指導者も自国の繁栄 = 大きくすることに挑戦してきたはずです。大きくすることなく、適正規模で反映させる。ビジネススクール時代に「ビジョナリーカンパニー」という企業のあり方を学びましたが、まさにその国家版でしょう。
世界中から乗り込んだ観光客たちは、ありそうでない、山のど真ん中にある飛行場にタラップから降り立ち、思い思いに写真撮影会。写真を撮らずにはいられない光景がお出迎えなのです。そして、それをせかすこともなく、せっかく来たのだから楽しんでいってください、というまなざしで、歴代5人の王様の看板が温かく向かえてくれたのでした。
世界中から乗り込んだ観光客たちは、ありそうでない、山のど真ん中にある飛行場にタラップから降り立ち、思い思いに写真撮影会。写真を撮らずにはいられない光景がお出迎えなのです。そして、それをせかすこともなく、せっかく来たのだから楽しんでいってください、というまなざしで、歴代5人の王様の看板が温かく向かえてくれたのでした。
ビザ
ビザが発行されたのは、出発2日前。しかも、メール添付の紙切れ一枚のみ。入国と出国のとき使うので、2枚プリントアウトしていってください、とのこと。しかも、他の人たちの名前とパスポート番号まで記載されている。個人情報管理のこの時代に、それらは無視してください、とのこと。うーん、何となくわかってきたぞー、ブータンがどんな感じか・・・と出発前からわくわくしていたのでした。
最初のトラブルもビザ
なんと、私のパスポート番号が間違って記載されていました。手続きに必要だからと、パスポートを預けることとなりました。旅行会社、シデブータンのガイドさんは「すみません」とひどく恐縮した様子。でも私は、パスポートを携帯していなくてもそれほど問題にならないくらいの国ならなおさら結構、と出だしから楽観主義全開でした。そして、パスポートなしで幸せの国ブータンの旅がいよいよ始まりました。
最初のトラブルもビザ
なんと、私のパスポート番号が間違って記載されていました。手続きに必要だからと、パスポートを預けることとなりました。旅行会社、シデブータンのガイドさんは「すみません」とひどく恐縮した様子。でも私は、パスポートを携帯していなくてもそれほど問題にならないくらいの国ならなおさら結構、と出だしから楽観主義全開でした。そして、パスポートなしで幸せの国ブータンの旅がいよいよ始まりました。
ガイドさんと運転手さんを雇う旅
ブータン旅行のシステムは、高くつきますがモノは考えようです。観光客はガイドさんと運転手さんを雇わなくてはなりません。通常3名からで、1人や2人での参加は割増料金がかかります。隣の国ネパールが、バックパッカーにも門戸を開いたところ、遺跡は荒らされ、お金も落としていかない、その教訓からブータンは「敬意を払って観光してくれる人しかこないでね」と、入国人数を制限しているのです。主要産業が水力発電と観光産業だからといえど、あまり観光地化してしまうと国の整備が追いつかないから、世界遺産にも登録はしない、という筋の通った方針。観光産業がちゃんと成り立つように、その産業に従事した人がちゃんと生計を立てられるように、雇用を確保できるシステムで観光客を迎え入れるのです。最初その話を聞いたとき、ガイドさんに当たり外れがあるんじゃないか、と思いましたが、私たちの運が良かっただけでなく、ガイドさんがはずれだったという話もあまり聞きませんでした。私たちのガイドさんはビカシュさん、運転手さんはちょっとシャイなSBさんでした。2人とも民族衣装を着ています。私が気に入ったのは黒いハイソックス。よく歩くからでしょう、足首がちゃんと引き締まっており似合うようにできているのです。
時差
ブータンまでの飛行機は一社しか飛んでません。その名もDruk Air、国営航空です。日本からはタイのバンコクを経由して入ります。日本とタイの時差は2時間、そして、タイとブータンの時差は1時間。なので、それほど身体に負担もありませんでした。
ピカチューとなんども唱えながら
これから6日間、ガイドさんたちと行動を共にします。名前を覚えなくては・・同夜って覚えたかというと、ガイドさんに声をかけようとするたびに頭の中で「ぴかチュー、 ぴかチュ、ビカシュ!」とたぐりよせるように名前を思い出すようにしました。 (上の写真がビカシュさんです)
看板のない道路
日本の観光地の辟易してしまうところは、どこに行っても看板看板があることです。ここ、ブータンではほとんど全く看板がありません。あるのはガソリンスタンドぐらいです。
信号もない
ブータンの道路には信号がありません。別な言い方をすると、信号がないぐらいの規模にしか交通量を増やさないことで、安全を確保しているのです。最も交通量が多い首都ティンブーの中心では、おまわりさんが手旗信号で交通をコントロールしています。
信号もない
ブータンの道路には信号がありません。別な言い方をすると、信号がないぐらいの規模にしか交通量を増やさないことで、安全を確保しているのです。最も交通量が多い首都ティンブーの中心では、おまわりさんが手旗信号で交通をコントロールしています。
ゾンとはいわば伝統建築のまま機能している県庁舎
ブータンめぐりで欠かせないのが「ゾン」という建物です。そして、ゾンを上から眺められる建物を「タゾン」というのだそうです。最初に連れて行かれたのが、この美術館でした。
Mindful Living in Bhutan
ブータンに来る前に、スペイン人の友人がお土産に持ってきてくれたこの本、ブータンのお土産屋さんではほとんどどこにでもおいてありました。有名な本なのでしょう。著者のプンツオク・タシさんはその美術館の館長さんなのだそうです。仏教の素地がない私が事前に読んでみましたが、内容がよく理解できなかったことを白状します。
Mindful Living in Bhutan
ブータンに来る前に、スペイン人の友人がお土産に持ってきてくれたこの本、ブータンのお土産屋さんではほとんどどこにでもおいてありました。有名な本なのでしょう。著者のプンツオク・タシさんはその美術館の館長さんなのだそうです。仏教の素地がない私が事前に読んでみましたが、内容がよく理解できなかったことを白状します。
Wise men control themselves
「聡明な人間は自分を律することができる」
美術館の壁にいくつかの言葉が書いてあったのですが、この一節のみ頭に残りました。
美術館の壁にいくつかの言葉が書いてあったのですが、この一節のみ頭に残りました。
質問の嵐
ドライブをしながら、たくさんの疑問をビカシュさんに浴びせました。
英語はみんなどうやって学ぶの?
ブータンには専門家が少ない。だから、専門家を海外から招聘しなくてはならない。そのためには公用語として英語を通じるようにしないと不便。だから教育の段階で子供たちに英語は基本教養として学ばせるのだそうです。
自分たちの国が幸せだということをどうやって知っていくの?
ブータンでは教育で洗脳することはしません。世界の歴史なども事実だけを淡々と教えます。その中から、結果的にブータンの人々は、私たちは幸せだと気づいていくのみです。教育では全てを教えないのです。本人が気づくように仕向けるのです。比べることで見つける幸せではなく、絶対的な幸せを自分で納得するためです。比べてしまうと不幸になってしまうからです。
ヨガ教室は普及しなかった?
私の友人も首都ティンプーでヨガ教室を開きましたが、実際ヨガはブータンでは全くと言っていいほど知られていません。今回訪れてその理由がわかりました。ヨガがいらないぐらい皆よく運動し、健やかに暮らしています。
病気の人はいないの?
もちろん、人間ですから病気になる人もいます。でも諸外国に比べると不養生からくる病気の人は少ないでしょう。病院にいくのに片道6時間ぐらいかかることもありますから、皆よく食べ、よく運動し、元気に暮らすよう心がけているのです。
ブータンには花嫁修業ってあるの?
伝統的なものが息づくブータンだからこそ、お嫁に行くときに身につけなくてはならない習わしがたくさんあるのではないかと思い、質問してみましたが、そんなものはないのだそうです。皆、自然と親から学び身につけて大人の女性になるのだそうです(理想的)強いて言えば、親孝行をすること、親の言うことを聞くことなのだそうです。
ブータンの王様のおさらい
3代目の王様:近代ブータンの父
4代目の王様:海外と門戸を開く GNH という概念を作る
5代目の王様:31才の若きプリンス、10月にはロイヤルウェディング!
インドと仲が良い
インドはいろんな国との友好に努力している印象があるが、ブータンも例外ではない。ブータンへの専門家や出稼ぎは、インドからが多い。食料の輸入もインドからが多い。もちろん文化も入ってきている。
休日はダーツ大会で日が暮れる
私たちが到着したのは土曜日だったので、人々はお仕事はお休み、空き地でダーツ大会に盛り上がっていた。日本であれば週末野球をするにしても、午前中だけ、午後だけ、というパターンが普通なのに、ここでは朝から、お昼ご飯をしっかりはさんで、午後まで対戦するのだという。二手に分かれて矢を投げあい、当たると歌を歌い踊りを踊る。それを延々と繰り返すのだが、カメラを向けても平気化とビカシュさんに尋ねると、観光立国だから皆写真を撮られることには慣れているとのこと。それでもピースをする輩などおらず、実に自然に被写体になってくれる。懐が、深い。
美術館にいた伝説のガイドさん
ブータンでは子供の頃からお坊さんになるのも珍しくはないが、美術館に功績をたたえられていた伝説のガイドさんは「お坊さんになるのは遅い方がいい。いろんな人生経験を積んでからの方がいいのだ」とおっしゃっていたとのこと。そして自ら出家し、五体投地 ( 五体すなわち両手・両膝・額を地面に投げ伏して、仏や高僧などを礼拝すること)で、場所は忘れたが気が遠くなるほど長い距離の聖地までの巡礼をこれで行ったのだそうだ。
じろじろ見られない快適さ
インドやアラブ、ヨーロッパの田舎に行くと、外国人である私たちはじろじろと見られることが多く、正直その視線に疲れてしまうことがある。ブータンに来て驚いたのは、誰もそんな失礼な眺め方をしないということ。じろじろ見られることが居心地が悪いことをわきまえているのか、それが自然なのかわからない。 (写真は首都ティンプーの町並みです)
信仰とは
主人の祖父が亡くなったとき、お葬式でお坊さんが話された「信仰」についてのお話「信仰とは、何があっても起こってもこれがあれば大丈夫と思える心の支えなのです」という言葉を、お寺にお参りし、五体投地をするブータンの人々をみて思い出しました。お祈りの仕方を教えてもらいました
私たちも郷に入りては郷の方法で、と、五体投地の仕方を教えていただきました。頭、口、胸で手を合わせ、膝間ついて頭を地面につけます。これを3回繰り返します。もちろんもっと繰り返してもかまいません。私たちは頭や口、心で悪いことを考え、罪深い人間になります。それをどうかお清めください、という気持ちで祈るのです。
私たちも郷に入りては郷の方法で、と、五体投地の仕方を教えていただきました。頭、口、胸で手を合わせ、膝間ついて頭を地面につけます。これを3回繰り返します。もちろんもっと繰り返してもかまいません。私たちは頭や口、心で悪いことを考え、罪深い人間になります。それをどうかお清めください、という気持ちで祈るのです。
ブータンのエコ
紙すき工場の見学に連れて行ってもらいました。昔ながらの方法で紙を作っています。こんなに丁寧に紙をつくられると、紙を大切にしないと、という気持ちにさせられます。そして、ブータンでは極力プラスチックバッグ(ビニール)を使わないのだそうです。買い物をしたときも、紙の袋や紙に包んでくれます。そういわれてみると、町中にビニールが落ちていないのです。
伝統を大切に守る姿に
今では民族衣装ではなく、GパンにTシャツが楽だから、という若者も増えてきているそうですが、観光業に携わる人はもちろんのこと、子供たちの制服としても民族衣装は人々の日常に当たり前のようになじんでいます。私たちが着物で暮らしているようなものです。普通であれば、時代劇にタイムスリップしたような感覚を覚えるのでしょうが、何の違和感もないのです。日本も、京都や奈良の一流校の制服を着物にしたらどうでしょうか。男性の着物なら女性より簡単です。男子校から始めてもらえれば日本も何かが変わると思います。自国の文化を大切にする姿勢に、私たちも自分たちの文化をもっと大切にしなくては、と思わせられるのはどの国を旅してでもですが、今回ほど説得力を以て痛感したことはありませんでした。
レモングラスのスプレー
ブータンのほとんどのお土産屋さんにはレモングラスのスプレーがおいてあります。実は私も日本にいた頃にブータンから帰ってきた友人にもらったのですが、これが使い勝手がいい。手頃な値段でとてもいいお土産になります。
中国でもないインドでもない
ブータンの風景は中国っぽくもありインドっぽくもあります。でも、決してそれらのどちらでもないのです。人も少なく、ゴミも落ちておらず、のどかで清潔な感じなのです。こんな山の中に都市としての首都があること自体が驚きであり、こんな山奥で携帯電話が通じ、人々が教養としての英語を操ることは奇跡のように感じられます。
ブータンでは時計回り
神社などに行くと、マニ車などがあります。到着したらまず、ぐるっと時計回りになぞっていくのがここブータンでの習わしです。
本当に幸せなのか、まだ疑問が残っていた
主人とシャワーのお湯が危うく、水洗トイレも流れないホテルの部屋で話したのは、ブータンの国民は本当に幸せなのか?幸せだと言いくるめられているだけなのではないか?という本音の疑問を打ち明けあいました。確かに料理はおいしいけど、ブータンの人々はあまりにも「これでいい」と飼いならされているような気がしてならない、と。しかし、幸せな人の定義は幸せだと思える人のこと。(それを楽観主義って言うんだよ、と主人は言った)でも、数日この国で過ごして、空に浮かぶ月を見ながら、情報化社会のもとどんどん近代化していくアジアの国の中、自分たちのペースを守り、意図的に農村社会の維持に努め、世界で最も先進的な「GNP」という概念を高らかにうたい、国民がそれについてきていること自体、簡単そうで簡単に成し遂げられることではない、とあらためてブータン王政を素晴らしいと思ったのでした。時に、攻めることより守ることの方が難しいことがあるものです。守り抜くことには勇気も努力もいるものです。
比べないという幸せに気づかされた
ブータンの幸せな国土を旅しながら気づいたこと、それは「私のふるさと日本には日本の素晴らしさがある」という、他の国を旅してもいつも思うありきたりの真理でした。でも今回はちょっと違います。圧倒的にブータンはGNH高そうで、明らかに日本は精神的な病巣が根強くはびこっている、と思ってすら、日本にはブータンにない秋の紅葉があり、世界最新鋭のウォッシュレットがあり、トイレは清潔で、寿司はおいしい。日本には日本の良さがある、それを大切に思う気持ちをもっと自覚(マインドフルネス)しなければ、という気持ちにさせられたのでした。私たちは忘れているだけなのです。
ブータンの人もお酒を飲む
農作業が終わると家で飲んだり、街に勤めている人はバーに寄ったり、ブータンの人々は聖人君子でもなく、ちゃんと私たちと同じように娯楽も楽しんでいるのです。ちなみにホテルのバーではウィスキーのショットは35ヌルタン(約70円)!ビールは一本150ヌルタン( 300円)。ローカルビールは3種類。レッドパンダ(赤いパンダではなく、アライグマのような動物)これは、酵母ビールのテイスト。そして Druk 11000 これは8%と強いビール。そして Druk Lager これが一番当たり障りのないビールです。そして高級ウイスキーと言えば K5。五代目の王様の戴冠を記念して作られた。街での価格が約900ヌルタン(1800円)1,800円でかなり高級な風味と主人は大喜びでした。
ブータンのGNHのもとになっている考え方
私たちは本当にいいガイドさんに恵まれました。とても日本語が上手で、日本で放送されるブータンについての番組のリサーチャーなどもやっているので、知識も豊富です。そのビカシュさんがGNHの元になっている考え方を説明してくれました。
家を建てるにも4本の柱が必要
(1)平等な経済発展 (格差があると不幸と感じる人が増える、確かに・・)
(2)環境を守ること ( 絶対的に大切なことです)
(3)文化を守ること ( 言うは易し、続けるは難し)
(4)良い政府 (汚職がある国の国民は不幸です)
でも、この4つの柱より、ブータンの人々の心に深く根ざしているモノの考え方があるのです。それは「 心理的な幸せ
共同体の活力
時間管理の大切さ 」です。
共同体の活力
時間管理の大切さ 」です。
まず、心理的な幸せについてですが、どんなに物質的に満たされても、心理的な平和を欠いた人は幸せになれない、という考え方が国民全体に浸透していることがすごい。だから、学校でも授業が始まる前に瞑想をするのだそうです。欲を持って勉強してもろくな学びは得られない。まず心を真っ白にして、謙虚な気持ちで学ぶことで、学びを幸せに活かすことができる。うーん、受験戦争が過酷な我が国の子供たちにも瞑想をさせたい。少なくとも我が子と一緒に勉強をするときは取り入れたい習慣です。何のために勉強をするのか、基本的なこと、初心に戻ることの戒めです。
次に、共同体の活力ですが、幸せな社会は簡単につくられるものではなく、一人一人の幸せが集まって生まれるもの。だからこそ、一人一人が社会を仕合せにするという自覚が必要であり、そのためには一人一人が生活し所属する共同体が活力のある存在でなければならないということ。だからブータンでは地方分権、権限委譲も積極的に行われているのです。
最後に時間管理を大切にすること。ブータンというと、のんびりした国。人々はゆっくり暮らしているというイメージがあります。それはその通りなのですが、実はそれはブータンの人々が時間を大切にしている賜物なのです。決して便利ではない社会で生きていくためには、限られた時間を何に使うのか、見積もって行動していくことの大切さを皆わかっています。だから、無為に時間を浪費することなく、朝はちゃんと起き、昼はちゃんと働き、夜は楽しくお酒を飲み、しっかり休むのです。普段はしっかり働き、お休みにはたっぷり遊ぶのです。私たちは先進国に暮らしているようで、実は著しく時間の奴隷になっています。電車に間に合うよう急いででかけ、余暇の時間もなく、夜更かしをし、時短生活で得た時間にまた詰め込んで過ごす。私が教えているリストラティブヨガにも実は同じようなヒントがあります。リストラティブヨガはだらだらと時間の許す限りヨガのポーズをし続けることではないのです。20分という時間を決めて、その時間をしっかり毎日の生活の中に自分のために確保し、その時間内で腹を据えて休み、心と身体の回復に積極的につとめるのです。時間は限られているからこそ、そして平等に与えられているからこそ、神様は人間に管理能力を授けてくださったはずなのです。
珍しい動物
顔がヤギで、身体は牛?
3000メートルの山小屋でグルメ
日本の登山の山小屋で食べれる食事はお世辞にもグルメとはいえないものばかり。その隔世感が好いという声もあるのですが、ここブータンでは3,000メートルの標高で結構いける味を楽しめます。もちろん山小屋には変わりなく、トイレも恐ろしく汚いのですが、食事はおいしい!
峠でティンシャを買いました。
ティンプーとプナカ村の間の峠にあるホテルの売店でティンシャを買いました。値段によって音質が違うのがわかり、興奮してしまいました。ティンシャにはブータンのマントラが書いてありました。
友人がいっていた大学
私の友人はちょうど入れ違いで数年ブータンの大学で教授をしていました。水力発電について教えていたそうです。せっかくなので大学もいってみました。とても山の奥!ここに頭脳が集結していると思うと、神秘的でした。
航一のブータンネーム:キレドジ
ビカシュさんがブータン人のホテルの従業員と話しながら、彼には「キレドジ」というブータンネームがぴったりだ、と言い出したところ、一同「全くその通りだ」とのことで、彼は初日から「キレドジ」と呼ばれることになりました。そして、いく所々で、彼の名前は「キレドジ」なんだというと、みな「あ~(納得)キレドジ~」と声を上げてくれたのでした。ドジとは仏さまが使う武器(短剣)のことです。リズムを取ったり、病気治癒祈願などに使われています。
Divine Madman (神聖なるただならぬ男)
ブータンの街には思わず顔を赤らめてしまうイラストや置物があります。これは 女性と遊ぶのが大好きでお酒好きだったDivine Madmanの男性器のシンボルなのです。
プナカでは彼のお寺にお参りに行きました。子宝のお寺でもあるそうです。航一がつけてもらったキレドジというブータンネームのキレもここにリンクしています。 お寺ではDivine Madmanは ドッパキレと呼ばれています。寺院では、天然の蓮の花が咲いていて、目を奪われました。お寺までは、田んぼの中を歩いていきます。牛ものどかに歩いています。
そうそう、キレドジという名前を聞いて航一「女たらしになるなよ」と言われていました。
プナカでは彼のお寺にお参りに行きました。子宝のお寺でもあるそうです。航一がつけてもらったキレドジというブータンネームのキレもここにリンクしています。 お寺ではDivine Madmanは ドッパキレと呼ばれています。寺院では、天然の蓮の花が咲いていて、目を奪われました。お寺までは、田んぼの中を歩いていきます。牛ものどかに歩いています。
そうそう、キレドジという名前を聞いて航一「女たらしになるなよ」と言われていました。
峠で会ったアスリートに触発されて
峠でお会いした自転車アスリートの方の楽しそうな様子を見て、思わず勝手に10年後の決意を固めてしまいました。航一が10歳になったら、ブータンに来て主人と一緒に自転車レースに参加させよう、そしてそのときもきっと変わっていないブータンをこの目で見に来ようと。ブータンの峠を完走できれば、世界中どこの道でも完走できるはずです。
峠でバスが燃えている?!
ブータンではよく、お香を焚いています。峠ではサイプレスの枝をお香として燃やしていたのですが、遠くから見たらまるでバスが燃えているようでびっくりしました。
空港がある街なのに魅力的なんて
普通、空港がある都市はなんかぱっとしないところが多いのですが、ここパロは空港があるのに水田風景がとても美しく、魅力的な街なのです。
空港がある街なのに魅力的なんて
普通、空港がある都市はなんかぱっとしないところが多いのですが、ここパロは空港があるのに水田風景がとても美しく、魅力的な街なのです。
川が合流する
プナかのゾンも男川と女川が合流するところに立てられています。ブータンではこのように、川が合流するところを良く見られます。そして、さらに驚くことに、合流する川の色が違っているのです。
ブータン一美しいプナカゾンを見下ろす高校
こんなところで学んだらいろんなことを深い気持ちで学べそうだ。国の歴史、文化、世界のこと。
ブータン一美しいプナカゾンを見下ろす高校
こんなところで学んだらいろんなことを深い気持ちで学べそうだ。国の歴史、文化、世界のこと。
ニコンのカメラ 41800円、ブータンの思い出 プライスレス
二人のカメラが壊れたので、思い切って買ったデジタル一眼レフ、プライスレスな思い出作りの役に立ちました。
紅茶ばっかり飲んでいた
ホテルにつくとチェックインの前に、コーヒーか紅茶はいかがですか?と声をかけてくれる。いつもはコーヒー派の私たちもなぜか気候に会っているのか紅茶を頼む。そして、紅茶にあうようなお菓子も添えてきてくれるのが心憎い。実際紅茶はインドからの輸入品なのですが、インド文化がすんなり入ってきているいい例です。
お腹いっぱいなのにいい匂い
満腹になると、もう匂いだけでも嫌!となるのが普通ですが、ブータン料理のすごいところは、満腹でレストランを出たあとも「ああ、いい匂い」とつぶやいてしまうことでした。たとえお寺にWisemen control themselves と書いてあっても、セルフコントロールができなくなってしまうビュッフェ形式の食事を続けていると、この言葉を思い出してセルフコントロールせねば、という気持ちになってきてしまう、これこそがビカシュさんが言っていた「学校ではね、全てを教えないんですよ。自分で気づくようになっているんです」の神髄ではなかろうか。
Use me と書いたゴミ箱
登山道にあるゴミ箱が使ってと話しかけてくるのです。
山道では特に車に酔いやすい
私が全く酔わなかったぐらい運転の上手なSBさんでしたが、さすが航ちゃんにはきつかったらしく、車の中ではおっぱいを飲んで静々と眠っていました。
男の人も赤ちゃんが大好き
ブータンで驚いたのは、男の人も赤ちゃんをとてもうまくあやすこと。ショ(おいで)
ブータンでの赤ちゃんのあやし方は、ショ( Come, おいで)、チチチチチ
ブータンでの赤ちゃんのあやし方は、ショ( Come, おいで)、チチチチチ
市場で購入:世界一硬いチーズ
凍み豆腐のように干したチーズが売っている。硬い。飴のように口の中に入れておくのだそうだ。 唐辛子はこちらでは香辛料ではなく、野菜だ。
バター茶
さすがに途中でギブアップ
ブータンのバターはとても風情があります。葉っぱで包んであるのです。エマダチ(唐辛子のチーズ煮)といい、チーズポテトといい、実はブータンは隠れた酪農王国。チーズ好きの私にはたまりませんでした。そして、極めつけは紅茶にバターを落し入れるバター茶。しっかり塩分入りのバターを使います。そのこってりさにはバター好きの私も最後まで飲みきれませんでした。
ブータンのバターはとても風情があります。葉っぱで包んであるのです。エマダチ(唐辛子のチーズ煮)といい、チーズポテトといい、実はブータンは隠れた酪農王国。チーズ好きの私にはたまりませんでした。そして、極めつけは紅茶にバターを落し入れるバター茶。しっかり塩分入りのバターを使います。そのこってりさにはバター好きの私も最後まで飲みきれませんでした。
お祭りの季節は予約を受けないんですよ
お祭りの季節はとにかく混んで、ホテルの部屋なども相部屋になったりするのだそうです。そして限られたリソースでのサービスとなるので、どうしてもサービスの質が低下してしまうのだそうです。それは嫌なので、シデブータンではお祭りの季節の予約は基本的には受け付けないのだそうです。
脱帽!
お寺にある色っぽい仏像
お寺にある色っぽい仏像
ブータンにある仏像には男性と女性が抱き合っているようなものもあります。これは知恵と知識の融合を意味するのだそうです。知恵は男性、知識は女性を意味するのだそうです。
ティンプーカット
一歳なのにもう9回も髪を切っている航一は、ここブータンでもヘアカットに挑戦することにしました(親の勝手)。ティンプーでも一番はやっているというインド人が経営する床屋さんで待つこと1時間、大人用の椅子の上に板を引いて、その上に航一は座らせられました。首にかけられたのは使い回しのシーツ、どうする?と言われたので、主人の即時の判断、そばにいたビカシュさんをさして「彼のように」そしてバリカンとはさみであっという間に航一は刈り上げられました。
ワンストーンプリーズの恐怖
パロのホテルでは石焼風呂という面白い体験をしました。一軒家の家族風呂の出で立ちなのですが、外では石焼職人さんが直径20cmほどの石を真っ赤に熱して待機してくれます。
お湯はどうやってわかしているかというと、別枠になっている湯船にこの石を放り込んで熱しているのです。そして、お湯が温くなってきたら大きな声で「ワンストーンプリーズ」と声をかけるのです。すると、低いところにある差し入れ口から、真っ赤に焼けた石が滑り台の上をコロコロ、ジャポン!と転がり込んでくるのです。もちろん、湯船とは別のお湯だめに落ちるので直接の被害はないのですが、これが怖い。息子は私が怖がると決まって連鎖して泣くのですが、そのときの私の恐怖は尋常ではなかったらしく、その後「ワンストーンプリーズ」という言葉にすらおびえているようでした。
もう一つ面白かったのは、ブータンでは毎日必ず何かしらのヨガをしていたのですが、石風呂の中は響きがいいのでせっかくなのでハミングブレスをしようよということになりました。息をはきながら、自分の頭の中でハミングを響かせる呼吸法です。二人で始めてみたものの、主人が「石焼職人さんたちが「あいつら悪魔だ!」と誤解して石をどんどん入れてくるかもしれない」と言い出したので、それは困ると思いやめました。
お湯はどうやってわかしているかというと、別枠になっている湯船にこの石を放り込んで熱しているのです。そして、お湯が温くなってきたら大きな声で「ワンストーンプリーズ」と声をかけるのです。すると、低いところにある差し入れ口から、真っ赤に焼けた石が滑り台の上をコロコロ、ジャポン!と転がり込んでくるのです。もちろん、湯船とは別のお湯だめに落ちるので直接の被害はないのですが、これが怖い。息子は私が怖がると決まって連鎖して泣くのですが、そのときの私の恐怖は尋常ではなかったらしく、その後「ワンストーンプリーズ」という言葉にすらおびえているようでした。
もう一つ面白かったのは、ブータンでは毎日必ず何かしらのヨガをしていたのですが、石風呂の中は響きがいいのでせっかくなのでハミングブレスをしようよということになりました。息をはきながら、自分の頭の中でハミングを響かせる呼吸法です。二人で始めてみたものの、主人が「石焼職人さんたちが「あいつら悪魔だ!」と誤解して石をどんどん入れてくるかもしれない」と言い出したので、それは困ると思いやめました。
ブータン風おんぶの仕方
ブータン旅行のいいところは、ガイドさんにある程度自分たちがやりたいアクティビティについてリクエストを言えることです。私は街で見かけた女性たちが赤ちゃんをおんぶする姿に釘付けだったので、機会があればあのおぶい方を教えてほしい、と伝えてありました。たまたま、Divine Madness の寺院に巡礼する水田で赤ちゃんを背負った女性たちとすれ違い、ビカシュさんはきちんと彼らに依頼しおぶい方講習をしてくれました。こういうサービスは本当にプライスレス、いや真心というのだと思います。
タイガーズネストまでの登山
途中のレストハウスまで一時間、岩肌に張り付くように立つ寺院「タイガーズネスト」まで、さらに一時間。上りは主人がブータン伝統のおんぶひもをかりておんぶしていきました。日本から持っていったおんぶひももあったのですが、やはりここはブータンスタイルで気持ちも高まります。主人は肩幅が広いせいか、息子のお尻が時々布からはずれてしまいます。ビカシュさんは「大変でしょう、父親予備軍の僕がいつでも変わりますよ」と言ってくださるのですが、主人は「いやここは僕も父親としての達成感が欲しくて」と、頂上まで背負って到達しました。一番助けてもらったのは私で、傘も水も持ってもらっている上に、私の荷物まで持ってもらい、私は一行に迷惑をかけないように、の一心で寡黙に登りました。だってここは高地。いつ高山病になってもおかしくない上に、貧血持ちの私が登山だなんて!脚幅を小さく、じぐざぐと、、。途中、ロバと馬の一行が私たちを追い越していきました。ギリシャのサントリーニ島にハネムーンに言ったとき、ロバ使いがロバを奮い立たせるのに「デラッ、デラッ」と言っていたのはその後しばらく私たちの間ではやりましたが、こんなに馬もロバも頑張っているのだから私も頑張らねば、という気持ちにさせられたのはこの国が殺生をせず動物たちと仲良く暮らしていることもあるかもしれません。帰りはカフェテリアまで私が背負いました。帰りは下りだから!と思っていたのですが、実はカフェテリアから寺院までは下りの階段がほとんどだったのです。なので逆向きは登り・・・次の角を曲がったらきっと平地だ、と思うこと30分、過酷でした。ようやくお昼ご飯、ビカシュさんがガイドさんの裏メニューであるブータンサルサを持ってきてくれました。主人はこれが一番おいしかったみたい。お腹ぺこぺこで3000m級の山に囲まれ食べる料理は、バリエーションとしてはいつもと同じなのですが、空腹は最大の調味料という私の座右の銘を立派に証明してくれました。そしてもう一つは、インド・ムンバイから来た女性とたまたま隣り合わせ、彼女が「ああ、やっぱり田舎っていいわ、インドはどこに行っても人、人だから」と言っていたことで、インドに行ったことのない主人もやっぱりブータンは正真正銘の田舎なんだということを確信したのでした。2時ぐらいに昼食を終えると、ぽつりぽつりと雨が。これから降りるのに一時間近くかかるのに、足下がぬかるんできてしまいます。私がおぶうか、主人がおぶうか、いや、ここは父親予備軍のビカシュさんに思い切ってお任せしよう!という決断は正しかったのです。次第に強さを増す雨に不安は増し、主人と私は手を携えて普通の3倍ぐらいのスピードで降りていきました。もちろん前を誘導するのは航一を背負いとても陽気なビカシュさん。もし主人が航一をみていたら、私のことを構えずに、私は間違いなく怖いよー怖いよー言いながらとても時間をかけて降りていくしかなかったと思います。このパーフェクトなチームワークで、予定の1/3 ほどの時間で下山することができました。ビカシュさん、とても陽気に歌を歌ったりしながら航一をなだめて降りてくれたので、喉が痛くなってないか心配になり、日本ののど飴をあげました。航一とビカシュさんの絆はこの一件でより深くなったと思います。10年後、頼もしい背中を覚えていることでしょう。
シンギングボール(おりん)セラピー
最終日、夕食までの時間はなにかSPAで珍しいメニューを、ということで、マッサージはタイでも受けられるのでここでしか受けられず、しかもインドや他の国と違ってボラレルこともないだろうと、Singing Bowl のセラピーを受けることにしました。楽な姿勢ですわって、音を聞くだけなのかな、と思ったら、二人ともマッサージベッドにうつぶせにされました。もちろん眼下にはボールに入った蓮の花。そして、仏教で「おりん」として知られるシンギングボールを足、腰、首の下に3つ乗せて音を響かせるセラピーは始まりました。身体の中を音が通り抜けていく不思議な感触で30分はあっという間に過ぎました。航一は「キレドジ」の名で、ブータン女性たちに大人気、預かってもらうことができました。
美味しくて、日本でも作れそうな料理
エマダチ :これなくしてはブータン料理は語れないでしょう。唐辛子のチーズ煮です。
赤米:寂しくなったら、スーパーで十穀米のもとを買ってきてやりすごします。
ジャガイモのチーズ煮:ニンニクと唐辛子と塩でこんなに美味しいのです。豚肉と大根と唐辛子の煮物
ワラビ:ショウガとニンニクでいためます
ブータンの料理本を買ってきました。850ヌルタン(1700円)結構いい値段がします。
赤米:寂しくなったら、スーパーで十穀米のもとを買ってきてやりすごします。
ジャガイモのチーズ煮:ニンニクと唐辛子と塩でこんなに美味しいのです。豚肉と大根と唐辛子の煮物
ワラビ:ショウガとニンニクでいためます
ブータンの料理本を買ってきました。850ヌルタン(1700円)結構いい値段がします。
松茸が・・・8本350円
私たちが行ったのが丁度松茸のシーズンでした。醤油を持参してよかった!人生で一度も食べたことのない量の松茸のホイル焼きをいただきました。ブータンでは普通、チーズと煮込んでしまうそうなのです。
神様のための一口
必ず食べる前に、神様のための一口をとりわけます。
お別れはつらい
最後、空港のチェックインカウンターにはガイドさんは入れません。ガラス越しにお別れを言うビカシュさんと航一の姿に、涙が出そうになりました。
2013.7.30