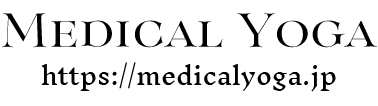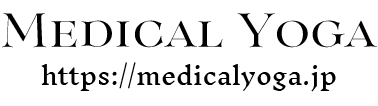認知症患者さんの意欲改善のポイントは前頭葉の血流
認知症に期待;抑肝散や釣藤散~NHKの番組より
高齢化の生理的特徴は
(1) 減る- 骨量、細胞
(2) 硬くなる – 関節、動脈
(3) 身体を一定に保つ機能の低下:体温、心拍数
(4) 免疫の低下による疾病の慢性化
そして、様々な疾患を身体に抱えるようになると、薬を多種類併用しなくてはならなくなったり、副作用に悩まされたりし始めるのです。それ自体、とても危険なことです。
(私の父も、薬の多種類併用によってびっくりするようなアレルギーに苦しめられました)
西洋薬だけでは対応しきれていない高齢者の精神症状に対して、最近、漢方薬の効果が注目されている。認知症の周辺症状を軽減し、介護ケアの負担を減らす期待がある。漢方は、現代の医療の中にも取り入れられ、その役割が改めて注目されている。最近、さまざまな研究データから、西洋薬だけでは対応しきれていなかった高齢者の精神症状に対し、漢方薬の「抑肝散」や「釣藤散」などの効果が確認されている。
アルツハイマー認知症に、現在処方されている西洋薬としては中核症状には塩酸ドネペシル、高血圧治療薬、高血小板薬などがあります。周辺症状には抗うつ薬を始め、漢方薬の効果が注目されています。例えば、西洋薬を使っていた患者さんに抑肝散や釣藤散を処方したところ、症状の緩和が見られたほか、微量循環による血流改善が見られたとのことです。
また、高齢者に睡眠薬を処方すると、睡眠には効果があるが筋肉がほぐれやすくなり、夜中に起きたときにふらつきによる転倒で怪我をするケースが増えてきているとのこと。このような方々に睡眠薬の量を減らし抑肝散を処方したところ睡眠の質そのものを改善する効果も見られたとのことです。
漢方では五臓の概念を用いてアプローチします。例えば、「肝」は西洋医学で言うところの肝臓に対応するわけではなく、筋肉の緊張を維持したり、精神活動の安定化をはかったりする役割を担っています。ですので、肝が虚弱になるとイライラしたり、攻撃的になったりするのです。この肝虚には抑肝散や釣藤散が効果的だと言われます。また、「腎」ですが、これも西洋医学で言うところの腎臓ではなく集中力の維持や視力、聴力、精神力の活性化に貢献するため、これが衰えると性欲の減退、冷え、いわゆる老化全般と言われる症状が現れてきます。これに効果的なのは八味地黄丸や六味丸だと言われています。(詳しくは専門家のアドバイスをご参照ください)
番組内で素敵だったのは、高齢者施設でみんなで歌を歌いながら、心を穏やかにしながら認知症の治療に取り組んでいるストーリーでした。ヨガも同じように穏やかな呼吸、穏やかな身体の動きで、血の巡りを改善できます。認知症患者さんの意欲改善のポイントは前頭葉の血流だとのことです。薬だけではなく、適度な刺激によって認知症の症状の改善は期待できる、ということを再認識させていただいた番組でした。